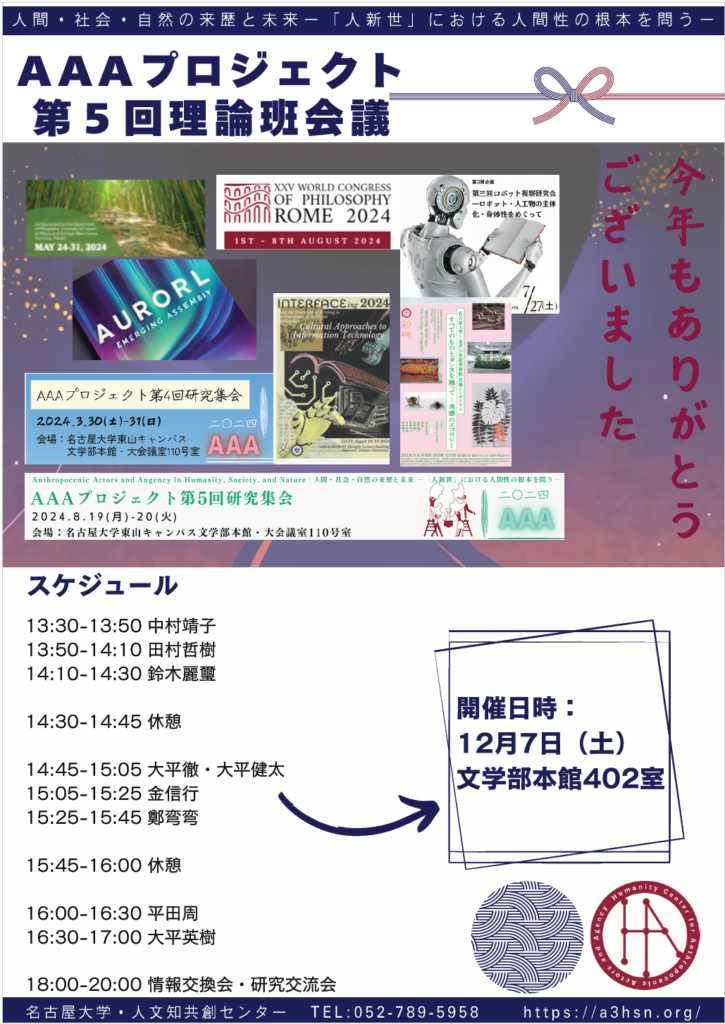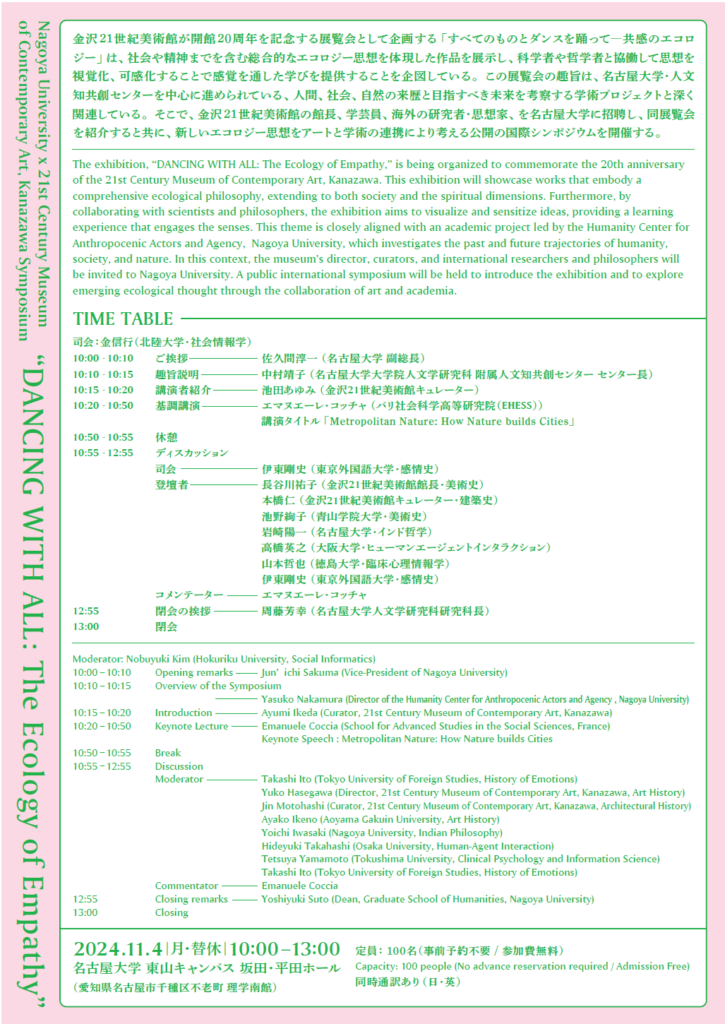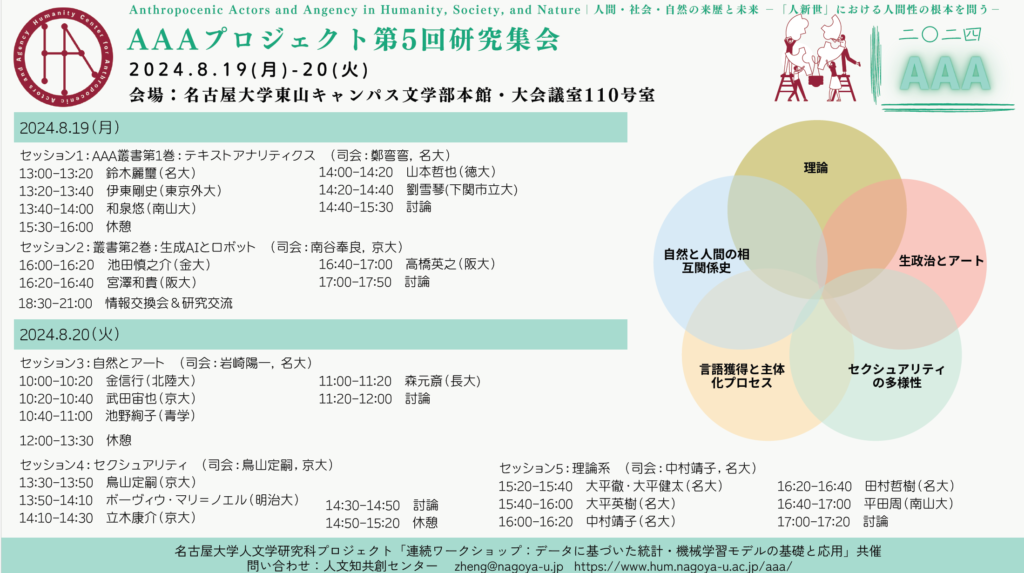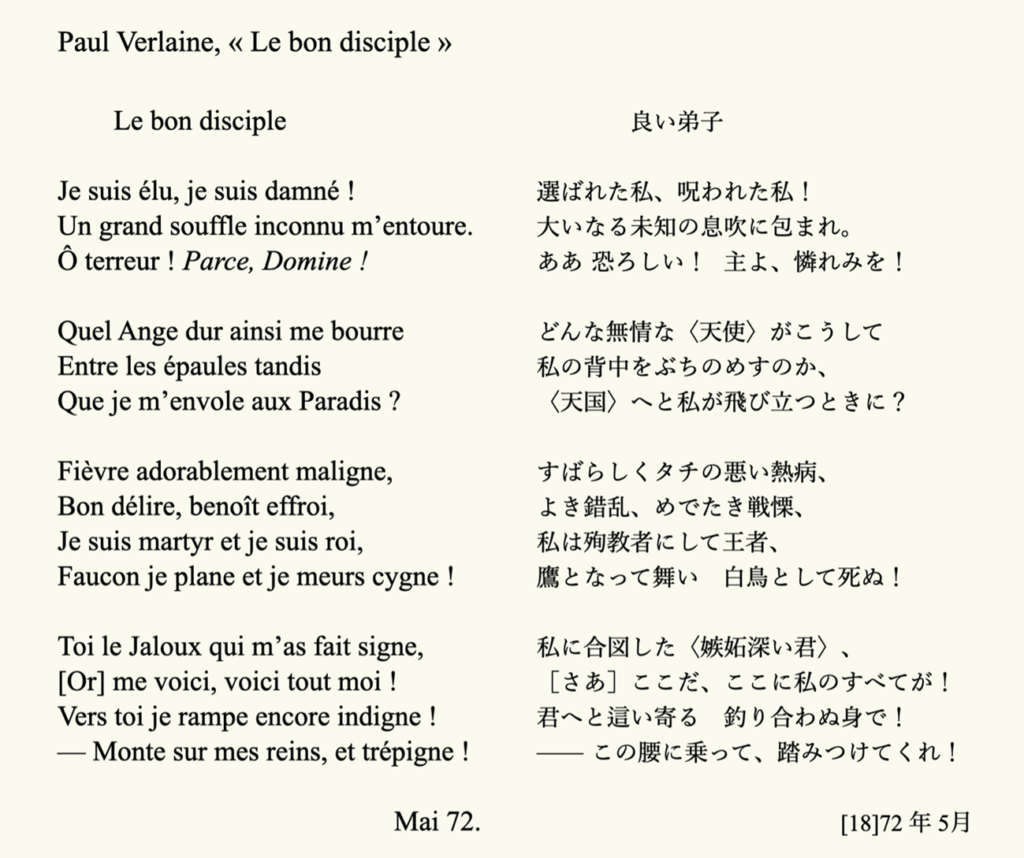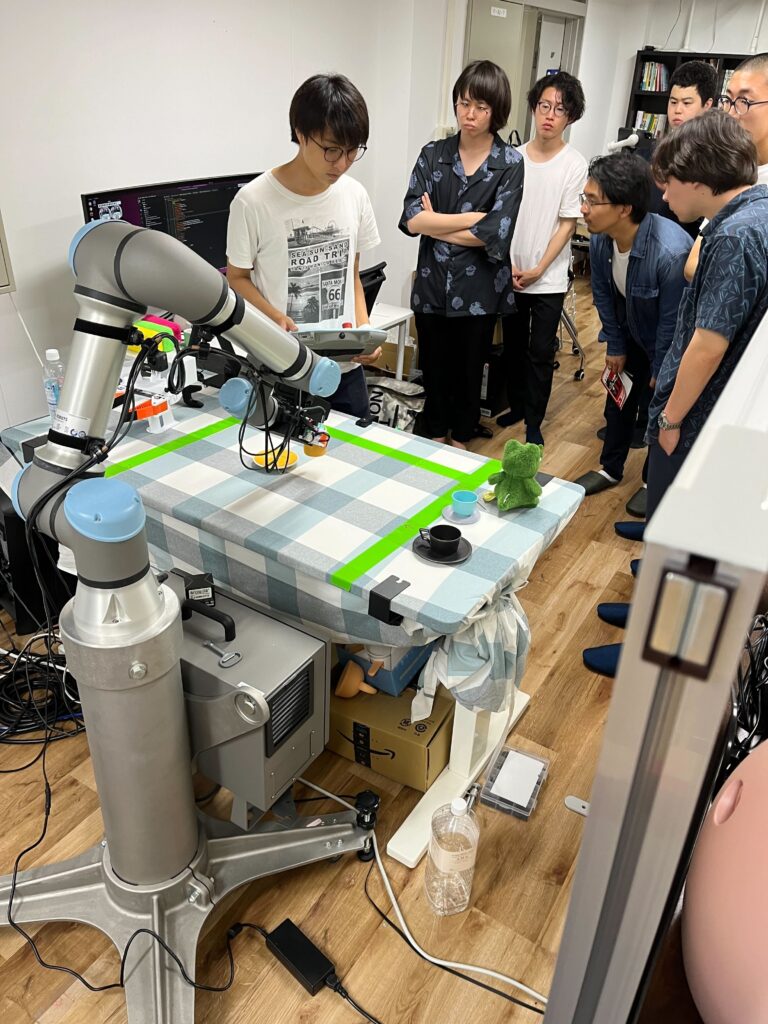2024年11月30日(土)に第一回創発知研究会を京都大学(@文学研究科部構内 文系学部校舎1F 多目的交流スペース「ぶんこも」)で開催しました。若手研究者のネットワーク形成と異分野間研究の可能性を模索する第一回では、南谷奉良(京大) 、金信行(北陸大) 、鄭弯弯(名大) 、鳥山定嗣(京大)が世話人を務め、15名の研究者の専門分野とその分野を学ぶための参考文献を紹介し、質疑応答を行いました今回の研究会では英米文学、現代アート、表象文化、インド哲学、哲学思想史、感情心理学、数学、機械学習、人工生命といった多様なアプローチが紹介されました。異分野融合の難しさは方法論や使用する概念の相違、問題意識の共有などがありますが、今回の研究会では無理に領域を重ねるのではなく、多様な異分野の研究を知ることからはじめました。以下に、各研究者からの発表内容要旨を紹介いたします。

第一研究発表
- 平井尚生(京都大学/英米文学、作家ヴァージニア・ウルフ、ジェンダー・フェミニズム)
20世紀英国の作家ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』(1928)を取り上げ、女性の生とフィクション=小説=虚構の関係についてのウルフの思想を論じた。特に、冒頭のオックスブリッジ大学の挿話において、ウルフが引用するチャールズ・ラム「休暇中のオックスフォード」(1820)との比較分析を行った。ラムは階級的・経済的理由から、大学教育を受けられなかったが、変装を通じて大学街に溶け込む一方で、同じく大学教育を受けていないウルフは女性であることから決して大学から受け入れられない。この比較分析を通じて、大学という知的生産の場における男性の特権性と女性の疎外が、フィクション=小説の手法によって、有効に描き出されていることを確認した。また、ラムは「エリア」という筆名を通して自らの個を強く表現している一方で、ウルフは、「メアリー・ビートン」という虚構的一人称にとって、歴史から疎外されてきた女性の普遍的な生を表現していることを明らかにした。
2. 飯沼洋子(京都大学/現代アート、ブラジル人アーティストのリジア・クラークについて研究)
第一回創発知研究会では、1960年代から70年代にかけた参加型アートにおける芸術経験の共有可能性について、個人研究の紹介を行いました。参加型アートの黎明期に活躍したブラジル人アーティスト、リジア・クラークの芸術実践では、それまでオブジェとしての芸術作品とそれを見つめる鑑賞者といった対立構図を回避し、鑑賞者の作品参加によって得られる芸術経験こそが作品であるとしました。そこでは参加者個人間、つまり私とあなた、私と周囲環境、主体と客体における関係性の再構築が目指されています。発表ではとくに、芸術実践〈食人よだれ〉を提示し、ブラジル近代芸術思想である「食人思想」と精神分析の理論「移行対象」との関連から、どのような主客の関係性が生じるのかについて簡潔に示しました。
3. 肖軼群(京都大学/現代イギリス小説、カズオ・イシグロ、マキューアンなど)
肖は、「『変身』の文学とカズオ・イシグロ」というタイトルで発表を行った。ここでいう「変身」とは、英語の”metamorphosis”に由来し、元のアイデンティティと決別し、完全に他者へと変容することを指す。カズオ・イシグロの作品はよく「記憶」や「自己欺瞞」などのテーマから論じられるが、それらのテーマの指向する先は、イシグロ自身の伝記的事実と関連している「変身願望」であると主張する。初期作品では日本人からイギリス人への変容、そして近年の作品ではクローン/ロボットから人間になろうとする姿が取り上げられている。設定上の違いはあれど、変身は一貫した大テーマとして繰り返し描かれている。イシグロは、変身を志向する主人公たちの世界を人物描写に限らず、作品内の環境描写などを含めて、多角的に提示しているとのことを発表で紹介した。
4. 福田安佐子(国際ファッション専門職大学/ゾンビ、ポストヒューマニズム、表象文化論)
発表では、まずゾンビ映画の歴史を概括した。各時代において描かれたモンスターはいずれも植民地主義や冷戦といった時代において登場した「異質な他者」である。さらに、現代において描かれるゾンビが、「理想の人間」のネガとして並置されることに着目し、その背景にはポストヒューマニズムのある種の「ねじれ」があることを分析した。
第二研究発表
- 楠元淳平(京都大学/アメリカ南部の作家ウィリアム・フォークナーの研究)
本研究では、ウィリアム・フォークナーの『アブサロム、アブサロム!』(1936)に、従来のフェミニズム理論が依拠しがちであった二分法的思考を乗り越える要素が含まれていることを示す。ジュディス・バトラーが述べるように、女性性の男性性に対する優位を主張するフェミニズムの言説はしばしばそれ自体男性中心主義的な身振りを反復しているが、フォークナーはそうした反復に陥らずに男性中心主義を批判しようと試みている。
2. 葉柳朝佳音(大阪大学/哲学思想史)
20世紀の生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは、生物学は生物を物理・科学的メカニズムに解体することなく、生のプロセス全体を扱うためには必要があると考え。そのために彼は生物身体の機能と構造から、生物が生きる環境との関係性の世界、すなわち環世界を記述しようと試みた。本研究では、ユクスキュルの環世界論について、おもに環世界における生物と主体の定義に注目して分析している。
3. 粥川恭輔(金沢大学/感情心理学、生理心理学)
人は他者の感情を推定する際に,他者の運動や感覚を自身の脳内でシミュレーションするとされている。その際観察者の顔では他者の表情が模倣される。一方で近年の研究では逆に,表情を変化させると他者の感情の推定に影響を与えることが示唆されている。しかしながら,表情の変化を支える運動野との関係性については明らかになっていない。そこで,本研究では一次運動野の興奮性と感情判断の関係性を調査する。
4. ジャスミン・デッラガーディア(千葉大学/宇宙心理学、宇宙倫理)
未提出
5. 田中基規(名古屋大学/インド哲学、ヒンドゥー教)
第1回創発知研究会では、自身の研究に関する発表を行った。発表の最初に、私がインド哲学、特にサーンキヤ思想を研究していることを伝えた。そして、サーンキヤ思想の特徴と、そのサーンキヤ思想で原理の一つとして考えられている自我意識に着目して、博士後期課程での研究を行っていることを述べた。最後に、他の参加者がインド哲学に馴染みが薄い可能性も考えて、3冊の研究に関連する新書を紹介した。
第三研究発表
- 大平健太(名古屋大学/数学、遅れ微分方程式についての研究)
微分方程式の説明として、ニュートンの運動方程式を具体例として挙げた。そこで基本的な数学・物理用語の説明も行った。遅れ微分方程式のイメージの説明を行った。初期区間条件を元に物理系が決まっていくことを列車に例えた。遅れ微分方程式の実例としてヘイズの方程式を挙げた。遅れを変化させることで物理系の性質が変化することをグラフで表現した。自身の研究している微分方程式 dX(t)/dt + atX(t) = bX(t-τ) とその解がガウシアンの重ね合わせで書けることを紹介した。物理系の概形もグラフにて紹介。
2. 浜野登(名古屋大学/エージェントベースモデル、文化的ニッチ構築、ゲーム理論、社会的粒子群、人工生命)
社会的粒子群モデルにおける文化的ニッチ構築について発表を行った。題材としたモデルの概要紹介や問いについて説明し、SNSや仮想空間といった交流の場における個体の環境改変が、社会集団の形成にどのような影響を与えるかを比較実験を通じて示した。代表的な実験設定に基づく複数の結果から得られた傾向を分析し、SNSプラットフォーム等の設計や運営において重要と考えられる環境構築についての示唆について論じた。
3. 高見滉平(大阪大学/機械学習、複数LMMエージェントによる社会規範や価値観の創成)
高見は,人にとって「良い雑談」を提供できる対話システムの構築を目指し,対話相手のセンチメント(感情の極性)を考慮して発話を選択する発話選択モデルを提案した.本モデルを用いた対話システムに関する被験者実験を実施し,アンケート結果からセンチメントを誘導する発話選択が対話の印象を向上させる可能性が示唆された.また,「良い対話とは何か」という問いを起点に,人間のハビトゥスとAI Alignment(AIの目標や行動の整合)の関連性を考察し,LLM(大規模言語モデル)エージェントにおいて,行動に結びついた価値観の創出が観察される可能性や,それがAI Alignmentに寄与する可能性についても言及した.
4. 浅野誉子(名古屋大学/大規模言語モデル、エージェントモデル、文化進化、ミーム、人工生命)
LLMに基づく会話エージェント間の相互作用による集団形成と文化進化の理解を目的に構成論的モデルを構築.エージェントは不変の遺伝形質(ポジティブ・ネガティブな単語)と他者から得る文化形質に関する文をLLMで生成し近傍相手と接近離反を繰返す.実験からポジティブ個体はネガティブ個体と比較して集団化する傾向が観察できた.文化形質伝達は,共有文化形質の出現,意味ベクトル分布の多方向への広がりなど多様化を促進した.
5. 福田聡也(大阪大学/LLMエージェントを用いた悪口がもたらす社会的ランクの低下に関しての研究)
LLMエージェントの主体化についての議論した。現状のLLMエージェントの自律性と主体性の関係について考え、道徳的行為者性と関係があるのではないかと考えた。そこで、LLMエージェントの道徳性を検証するために悪口が与える影響をシミュレーションする手法について検討した。また、人文学の観点では悪口と社会ランクの関連性が大きいと提言されているため、LLMエージェントの世界に社会ランクを導入する手法についても検討した。シミュレーションする際の現状の課題を共有し、それに関して有意義な議論を行うことができた。